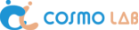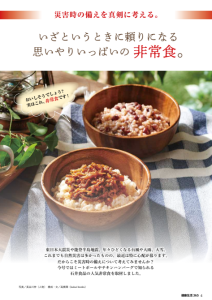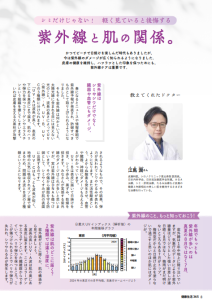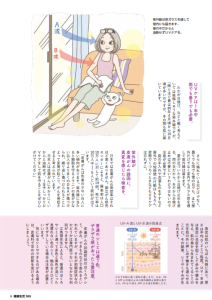- シニア調査
作成日:2025.08.21 最終更新日:2025.08.29
シニア向けの雑誌・Web媒体8選!高齢者に向けた効果的な媒体選びをご紹介
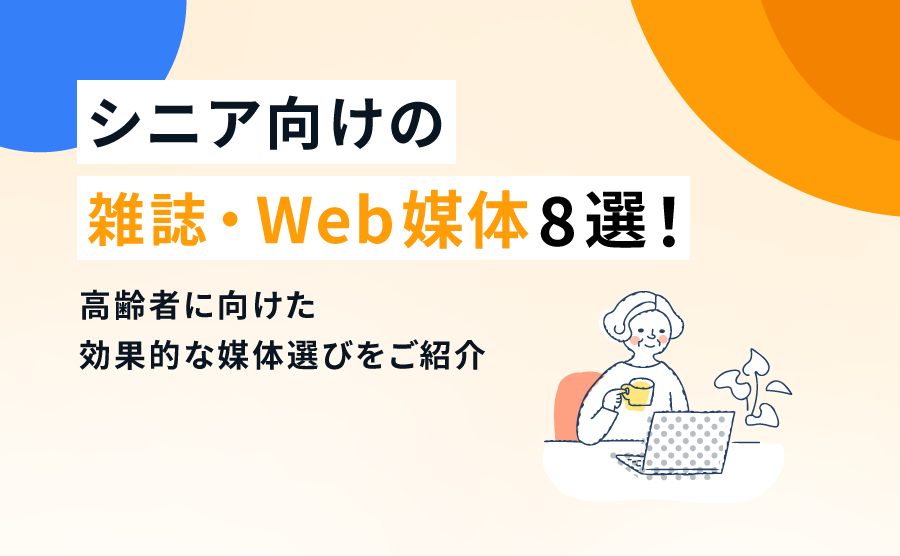
シニアマーケティングを成功させたい場合には、適切な媒体を選ぶことが大切です。しかし、「どの媒体を選べばよいか?」や「そもそも効果的な方法がわからない」などと、悩む人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、シニア層に響く媒体選びについて解説します。昔から「根強い人気を誇る紙媒体」と、利用が拡大している「Web媒体」について、具体的な事例もご紹介します。効果的なシニア向け媒体を選びたい場合には、ぜひ本記事をお役立てください。
目次
シニア向け媒体の現状と傾向

日本の高齢者人口は約3,600万人にのぼり、市場規模は100兆円を超える見通しといわれています。(参考:総務省統計局)
シニア市場が拡大するなかで、シニアの情報収集手段は多様化していることも事実です。以前から主要な情報源であった紙媒体(雑誌・新聞など)は、依然として高い支持を得ています。しかし、近年ではスマートフォンやタブレットの普及に伴い、WebサイトやSNSといったデジタル媒体の利用も拡大しています。そのため、ターゲットとするシニア層のライフスタイルや情報感度に合わせて、最適な媒体を見極めることが重要です。
シニアの世代別に見た媒体の利用傾向
シニアとひとくちにいっても、情報収集の方法は年齢によって異なる傾向にあります。
例えば、前期高齢者といわれる「65歳~74歳」は、インターネットやスマートフォンを積極的に活用する人も多いでしょう。YouTube・LINE・ニュースサイトなど、デジタル媒体の利用も増加傾向にあります。一方の後期高齢者(75歳以上)は、デジタルデバイスに不慣れな方も多く、新聞・テレビといった紙媒体や放送媒体に依存する人も多いでしょう。
とはいえ、健康状態・生活スタイル・デジタルへの抵抗感には個人差があるため、一律な判断は禁物です。ターゲット層の状況を配慮しつつ、最適な媒体を選ぶことが大切です。
参考:総務省情報通信政策研究所「情報通信白書令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 (概要)」
シニアが媒体を選ぶ際の特徴を知る

シニアに向けて効果的なアプローチをするには、ターゲットが媒体を選ぶ基準を知ることが大切です。ターゲットの心理や行動パターンを把握することで、より心に響く媒体選びが可能になるでしょう。
情報の質を重視する
多くのシニアは、長年の人生経験から、情報の信頼性を重視する傾向にあります。特に、健康や資産といった生活に直結する情報に対して顕著だといえます。
情報の信頼性を判断するために、掲載されている情報が「誰によって」「どのような意図で」発信されているのかを見極めたい人も多いでしょう。そのため、専門家の見解や信頼できる第三者からの評価や認証がある媒体は、受け入れられやすい傾向にあります。
慣れ親しんだ形式・ブランドを選ぶ傾向
シニアは、「慣れ親しむ新聞や雑誌」「いつも見ているテレビ番組やラジオ番組」など、生活の一部となっているメディアを優先して選ぶ傾向にあります。なぜなら、「手間をかけたくない」「新しい使い方を覚えるのは億劫」などの気持ちがあるからです。また、慣れ親しんだ情報源に対する安心感もあるでしょう。
新たなメディアに興味を持った場合でも、知っているブランドや信頼できる企業が提供するものであれば、心理的なハードルが下がり試しやすくなります。
口コミや周囲の推奨を重視
「誰かのお墨付き」や「みんながよいといっている」情報に安心感を覚え、それに基づいて行動するシニアも多いでしょう。「あの雑誌は役に立つよ」「このサイトは使いやすいよ」といった同世代や身近な人のリアルな声は、信頼性が高く、実際に試すきっかけになり得ます。また、共通の趣味を持つコミュニティ内での口コミや、実際にサービスを利用した人の率直な感想は、購買行動や媒体への関心を強く後押しすることがあります。
手に取りやすさを重視
シニアにとって、媒体にアクセスしやすいことも重要です。「アクセスのしやすさ」には、手に取りやすい、デジタルで使いやすいなどの要素が含まれます。例えば、「近所のコンビニエンスストアで手軽に買える雑誌」「郵便受けに届くフリーペーパー・会報誌」などは、自然と情報に触れる機会を作れるでしょう。
インターネット媒体の場合にも、画面が見やすかったり、直感的に操作できたりするウェブサイトやアプリが好まれる傾向にあります。
企業がシニア向け媒体を選ぶ際の3つのポイント

シニア層に効果的なアプローチをしたい場合、媒体の選定が重要です。ここでは、シニア向け媒体を選ぶ際に押さえておくとよい「3つのポイント」を紹介します。
ターゲット層との親和性がある
シニア向け媒体を選ぶ際に、基本かつ重要なのは、「媒体の読者層と自社のターゲットが一致するか」です。まずは、媒体の読者データ(年齢層・性別・居住地・興味関心など)を分析しましょう。そのうえで、自社が「解決できる課題」や「提供する価値」が、媒体の読者層に響くかを考えます。また、過去にその媒体で掲載された広告や成功事例も参考にしながら、自社の商品・サービスに対する読者の関心度や、購入につながる可能性を見極めるのもよいでしょう。
媒体の信頼レベルを評価する
多くのシニアは、情報の信頼性を重視する傾向にあります。したがって、広告を掲載する媒体のブランド力や、読者からの信頼度を見極めることも大切です。発行元の実績や歴史・編集方針・特定分野での専門性などを確認し、自社のブランドイメージと合うかを比較検討しましょう。信頼性の高い媒体に出稿することで、自社の商品・サービスに対してより安心感を持ってもらいやすくなります。結果として、購買意欲の向上が期待できます。
費用対効果を検証する
広告を出稿する際には、費用対効果の検証が欠かせません。広告は投資であるという意識を忘れず、費用対効果が得られるかを見極めることが、媒体選びには不可欠です。
広告費だけでなく、その費用によって期待できる成果(例:認知度の向上/資料請求件数/最終的な売上)を具体的に試算しましょう。また、複数の媒体で比較することが大切です。過去に似た広告を出稿した実績データがあれば、そのデータを参考にし、効果を予測することも可能です。
【雑誌編】多くの人に愛読される!シニア向け雑誌5選

多くのシニアに親しまれ、高い信頼を得ている雑誌は、現在でも強力な広告媒体だといえます。デジタル化が進む昨今でも、紙の雑誌には「じっくり読める」「手元に残せる」といった特徴があり、シニア世代の心にしっかりと届いています。
ここでは、シニアからの支持が高く、マーケティング効果も期待できる雑誌を厳選してご紹介します。
健康生活365
『健康生活365』は、健康と生活をテーマにしたシニア向けの会報誌です。シニアマーケティングに強いコスモラボが、年2回発行しており、約8万人の会員に届けられています。健康コラム・シニア向けエクササイズ・社会貢献活動の紹介・防災関連特集など、シニアの暮らしに役立つ多彩な情報を掲載しています。
会報誌という特性上、読者からの信頼度も高いことが特徴です。また会報誌はじっくりと読まれる傾向にあり、詳細な情報やストーリーを伝えるのにも適します。会員限定のクローズドな環境であるため、高いエンゲージメント率も期待できます。
【主な読者層】
健康意識が高く、活動的なアクティブシニア層
【適する商材】
健康食品・サプリメント・化粧品・介護用品・運動器具・シニア向け旅行商品・防災グッズ・金融商品(健康関連保険など)
~以下のページをサンプルとしてご覧いただけます。~
【非常食特集(石井食品協力)誌面】
【紫外線と健康特集ページ】
ハルメク
『ハルメク』は、50代からの女性をターゲットとした女性誌です。健康・美容・ファッション・旅行・マネーといった幅広いテーマを扱い、女性読者の好奇心を刺激します。定期購読者が多いため、継続的な情報提供やブランドロイヤリティの構築にも適するでしょう。
【主な読者層】
購買意欲が高く、新たなライフスタイルや知識の獲得に積極的なアクティブシニア女性
【適する商材】
健康食品・化粧品・ファッションアイテム・旅行商品・保険・不動産・カルチャースクールなど
サライ
『サライ』は、小学館が発行する男性向けのライフスタイル誌です。文化・歴史・美術・旅・食・趣味といった質の高い情報を幅広く提供しています。富裕者や高所得者層へのリーチが可能であり、商品の背景やストーリー性を重視する読者に響きやすいでしょう。
【主な読者層】
経済的にゆとりがあり、本物志向で教養の高い男性シニア
【適する商材】
高品質な食品や飲料・旅行商品(ラグジュアリー層向け)・高級時計・骨董品・趣味関連(ゴルフ、オーディオなど)・資産運用サービスなど
家の光
『家の光』は、JAグループが発行する、農村地域を中心に読まれている月刊誌です。農業や食に関する情報だけでなく、健康・暮らし・手芸・料理・家族といった幅広い生活情報を提供しています。読者の生活に寄り添う温かな誌面が特徴で、地域コミュニティへの影響力も期待できます。
【主な読者層】
全国のJA組合員を中心に、地域社会に根ざした生活を送るシニア
【適する商材】
食料品・農業関連資材・日用品・健康食品・地方産品・地域の観光情報など
きょうの健康
『きょうの健康』は、NHK出版が発行する「NHKのテレビ番組と連動」した健康情報誌です。病気の予防・治療法・健康維持のための生活習慣など、医学に基づいた情報を提供しています。読者が真剣に健康情報を求めているため、関連する商品の購買につながりやすいでしょう。
【主な読者層】
自身の健康に関心を持つシニア層全般。健康不安を抱える層から、健康維持に努めるアクティブシニアまで幅広い。
【適する商材】
医薬品・サプリメント・医療機器・健康食品・健康器具・介護用品・健康診断サービス・医療機関の紹介など
【Web編】デジタル活用シニアも増加中!Web媒体3選

スマートフォンを使いこなし、インターネットで情報収集や交流を楽しむシニアが増えています。そのため、Web媒体も無視できない強力な広告チャネルだといえます。ここでは、デジタルを活用するシニアに効果的な「注目すべきWeb媒体」をご紹介します。
趣味人倶楽部(しゅみーとくらぶ)
『趣味人倶楽部』は、共通の趣味を通じて交流できるシニア向けSNSコミュニティです。ブログ・イベント情報・掲示板などでの交流が行われるほか、リアルなオフ会が開催されることもあります。 趣味という共通の関心でつながるコミュニティのため、ターゲティング精度が高い点も魅力です。ユーザーの「好き」を起点とした広告は、自然な形で受け入れられやすいでしょう。
【主な読者層】
50代から70代が多く、趣味を楽しみたいアクティブシニア
【適する商材】
旅行商品・習い事・趣味関連グッズ(カメラ、登山用品、楽器など)・健康や美容関連サービス(※趣味を続けるためのもの)・イベントやセミナー情報など
おしるこ
『おしるこ』は、セカンドライフ世代に向けた「匿名のコミュニティアプリ」です。顔出し不要で匿名で利用できるため、気軽に参加できます。健康情報・日常のちょっとした疑問・趣味・ライフスタイルなど、幅広いテーマで意見交換が行われています。
ユーザーは日常生活の情報を求めているため、日常生活に寄り添うような「生活密着型の広告」も効果的でしょう。
【主な読者層】
50代以上で、オンラインでの交流を通じて新たなつながりや刺激を求める層
【適する商材】
健康食品・日用品・ライフスタイル改善サービス・オンライン講座・趣味関連・地域イベント情報・終活関連サービス・金融商品など
Slownet(スローネット)
『Slownet(スローネット)』は、人生の「後半」を楽しむ情報を提供するウェブマガジンです。専門家による健康コラム・旅行記・文化イベント紹介・終活に関する解説記事・著名人へのインタビューなど、知的好奇心と生活の質を高めるような記事が掲載されています。質の高いコンテンツと共に広告が掲載されるため、ブランドイメージを重視したい企業に適するでしょう。
【主な読者層】
50代後半から70代のアクティブシニアで、心豊かな生活や新しいライフスタイルのヒントを求める層
【適する商材】
旅行商品・イベントのチケット・生涯学習講座・金融商品・健康器具・高品質な日用品・趣味関連など
シニア向け媒体選びでよくある失敗パターン
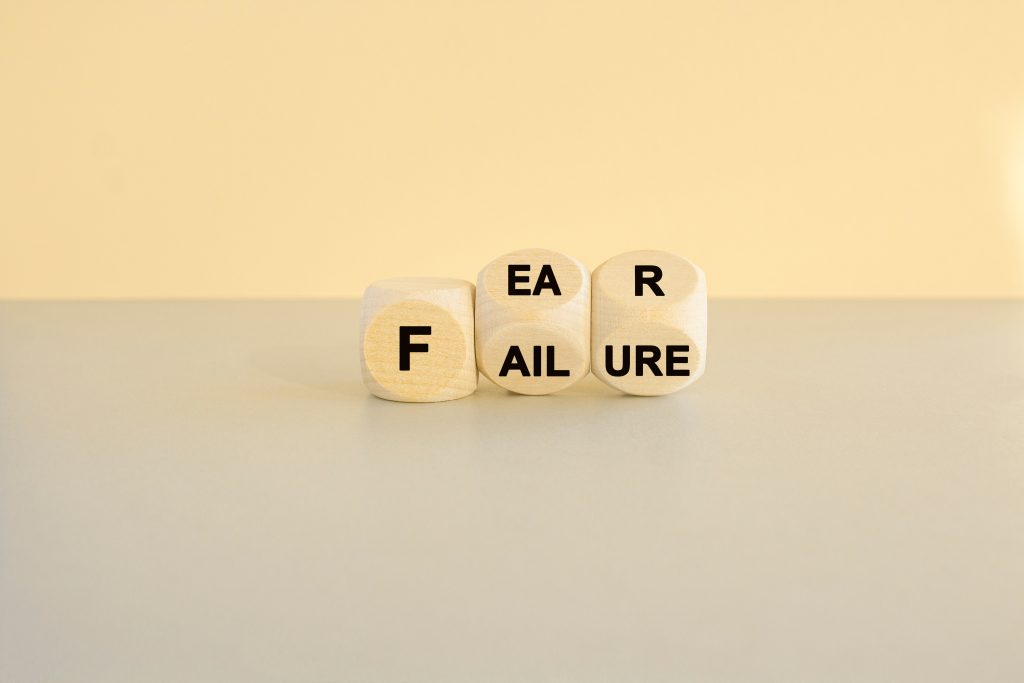
ここでは、多くの企業が陥りがちな媒体選びの落とし穴について、4つのパターンに分けて解説します。失敗パターンを回避することで、シニアマーケティング成功により近づけるでしょう。
ターゲット層と媒体読者層がミスマッチ
シニアと一括りにしても、年代・性別・ライフスタイルなどは多岐にわたります。例えば、60代前半の健康なシニアをターゲットにした商品を、70代後半が中心の「健康面に特化した媒体」でPRしても期待する反応は得にくいでしょう。
また男性向けの商品を、女性読者が多く購読する誌面に掲載しても、関心を持ってもらえる可能性は低いといえます。
アクセス数や読者数だけで媒体を選定
Web媒体のPV数や雑誌の発行部数など、表面的な数字だけで媒体を選ぶと、失敗する可能性があります。数字は重要なものの、それだけでは「リーチしたい層に届いているか」「広告がどれだけ読まれ、行動につながったか」は判断できません。
例えばWebサイトであれば、PV数だけでなく、サイト滞在時間・回遊率・コンバージョン率・フォロワーの属性も確認する必要があります。
競合他社との差別化を考慮していない
競合他社がすでに出稿している媒体に参入した場合に、自社の広告が埋もれる可能性があります。激しい価格競争に巻き込まれたり、広告効果が薄れたりするリスクも否定できません。
媒体を選ぶ際には、競合他社の出稿状況を調査し、自社の広告がどのように差別化できるかを考える視点が不可欠です。「ニッチな媒体を選ぶ」「新しい切り口での広告展開を検討する」など、戦略的な対応も求められます。
効果測定の体制に不備がある
シニア層向けマーケティングでは、効果が現れるまでに時間がかかる傾向にあります。多くのシニアは、情報をじっくりと比較・検討し、行動に移すまでに時間をかけることが多いためです。そのため、短期間の数値だけで施策の成否を判断すると、本来は成功する可能性のある取り組みを見落とすことがあります。したがって、広告を出す前に、効果測定する期間や評価の指標を決めておくとよいでしょう。
シニア向けの媒体選びを成功させるポイント

ここでは、限られた予算で最大限の成果を引き出すために、意識すべきポイントをご紹介します。成功ポイントを踏まえることで、最適な媒体を選べるでしょう。
年齢層を細分化してターゲティングする
シニアの情報収集パターンは、年齢層によって異なる傾向にあります。例えば「前期高齢者(65歳~74歳)」は、紙とデジタルを併用するケースも多いでしょう。そのなかでも、SNSを活用する人もいれば、Web検索を中心として情報収集する人もいます。また「後期高齢者(75歳以上)」も一括りにはできず、紙媒体中心の人もいれば、家族のサポートを受けてデジタルサービスを使う人も見受けられます。
そのため、年齢層を細分化したうえで、同じ年代のなかでも生活環境・デジタルリテラシー・関心といった「個々の属性ごと」にターゲットを分ける必要があるでしょう。
信頼性の高い媒体を優先的に選ぶ
シニアは人生経験が豊富なことから、情報の質と信頼性を重視する傾向にあります。そのため、広告を掲載する媒体選びでは、発行元の実績・編集方針・特定分野における専門性などを確認し、権威性のある媒体を選択することも一案です。特に、健康や資産運用といった「シニアからの関心が高く重要度の高い商材」では、専門家の監修がある媒体や第三者機関が評価する媒体を選ぶとよいでしょう。信頼性の高い媒体に出稿することで、読者からの信頼や広告効果を高めやすくなります。
読者の生活動線に合わせた媒体を選定する
シニアは、普段使い慣れていて、無理なく利用できる媒体を好む傾向にあります。そのため、彼らの日常生活に溶けこむ媒体を選定することが大切です。
例えば、購読している新聞や雑誌や、普段利用する店舗で手に取れるフリーペーパーや、スムーズに閲覧できるWebサイトなどが該当します。また、特定のコミュニティから定期的に発送される会報誌も、高確率で目を通してもらえる傾向にあります。ターゲットの生活パターンや情報収集の方法を理解し、無理なく情報に触れられる媒体を選ぶことがポイントです。
複数媒体の組み合わせでリーチを最大化する
シニア層の情報収集手段は、紙とデジタルが混在しているのが現状です。情報収集の多様性に対応すべく、単一の媒体に頼るのではなく、複数の媒体を組み合わせる「クロスメディア戦略」もおすすめです。例えば、紙媒体でブランド認知を高めつつ、Web媒体でより詳細な情報提供や資料請求への誘導を行うといった方法も考えられます。各媒体の強みを活かしながら組み合わせることで、より広範かつ深いアプローチが可能になるでしょう。
コスモラボが提案する最適な媒体選び
多くの高齢者向け媒体を目にすると、「自社に最適な媒体はどれだろう」「紙とWeb、どちらに力を入れたらよいか」といった悩みは尽きないものです。
そういう中で、多くのシニア会員に直接情報を届けられる会報誌はおすすめです。会報誌には、「信頼感の高さ」「確実に届く」「ターゲットが明確」という利点が揃っています。狙いたい層に直接メッセージを届けられるため、効果的なPRも期待できるでしょう。
コスモラボは、全国に20万人のシニア会員が在籍し、180件以上のシニア向け調査を行った実績があります。また会報誌「健康生活365」を定期発行しており、健康コラムや社会活動の紹介・防災関連特集など、シニアに役立つさまざまな情報をお届けしています。
「シニア層へ効果的に情報を届けたい」「プロモーションを成功させたい」とお考えの場合には、ぜひ一度ご相談ください。
シニア向け媒体選びで成果を上げるために
シニア層向けの媒体施策で成果を上げるには、まず「どのようなシニアに何を伝えるか」というターゲット設定が不可欠です。次に、信頼できる情報を発信し、ターゲットに合わせて媒体やチャネルを使い分けることが求められます。過去の失敗パターンを把握し回避することも、成功への近道です。これらを踏まえたうえで、自社にとって最適な媒体を選び抜くことが、ビジネス成功への大切なステップだといえるでしょう。